\24時間OK/
\平日9-16時 土日祝9-18時/
\無料、お気軽に!/
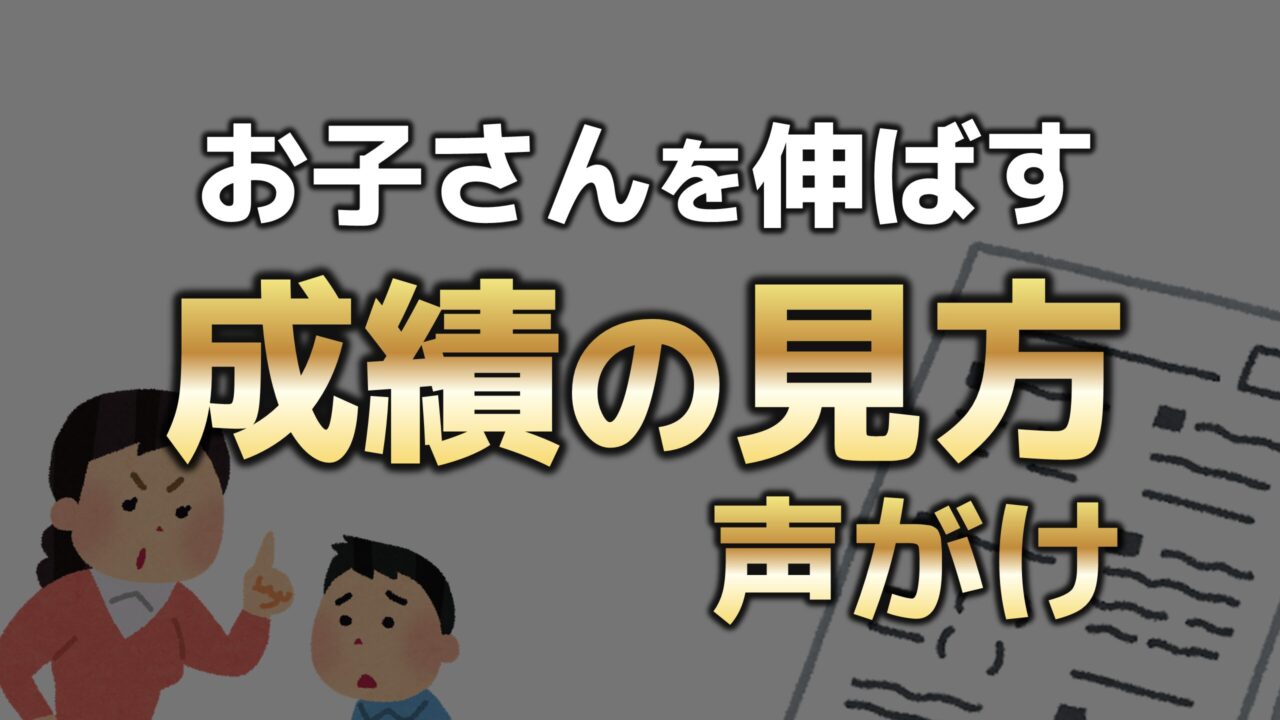
当塾の塾生・保護者のみなさん向けの解説です。中学生の保護者のみなさんが成績を見るときに、気をつけるポイントを解説しています。特に中2、中3とテストの難易度が上がってきます。だから点数は下がっていくのが自然です。勉強ができなくなっているわけでもないですし、サボっているわけでもないです。平均点と比べどれだけ高いか、低いかで見るようにしてください。
中1の最初のテストは平均点が330点。でも中2のテストでは平均点が200点。実に130点も平均点が下がっています。すると、400点取れていた子は、270点まで下がるのが自然です。それは成績が下がったわけではなく、バカになったわけではなく、テストが難しくなったのです。だから、平均点とくらべてどれだけ点数が高いか(低いか)で成績を見るようにしてください。決して点数で単純に比較をしないでください。
英語90点だった!(平均点80点)
→平均点+10点
→ちょいできてる。(偏差値55)
英語70点だった…(平均点40点)
→平均点+30点
→超できてる。(偏差値65)
このケースだと、70点の方がいいですね。平均点よりどれくらい良いか悪いかで出来具合をつかみます。
テスト結果が悪くて怒るのはあまりおすすめできません。子供に嫌われて、子供が自分の悩みを相談してくれなくなります。「最近、うちの子反抗期でね-」と親御さんはよく言いますが、お子さんが親に話しても意味がないと思っているのかもしれません。そうなると悲しいですよね。本人も結果が出なくて悲しい思いをしている。本人なりには努力をしたつもりであった。そんなときに、「あんたなんて点数とってんの!」と母親に怒られる。イヤですよねぇ。
テストは調子のいいときもあれば、悪いときもあります。スポーツと一緒です。たまたま打てることもあれば、たまたま打てないこともある。勉強も自分の得意分野が多く出題された。テスト期間に自分の部活だけ試合があったり十分に勉強ができなかった。多少、波はあります。だから短期的にどうこうでなく、長期的にみて実力がわかる。5回のテストの平均値がお子さんの実力と考えるぐらいでちょうど良いです。
計算の多いテストなら、計算力がものをいいます。応用問題が多いテストなら、応用力がとわれます。テストの出題の仕方で、結果の出方は異なります。お子さんが簡単な問題はできるけど、応用問題ができないタイプなら定期はとれるでしょうけど、実力テストは取れなかったりします。逆にあまり暗記系の追い込みはしていないけど、よく考えて勉強しているタイプは実力(確認)テストで点数が取れます。タイプです。
健康診断で数値だけが並んでいても、それがいいのか悪いのかわかりません。基準値があれば良いか悪いかがわかりますね。同様に、自分の子どもの点数だけだとそれがいいのか悪いのかわからないです。同年代の子と比較することで初めて客観的に把握できます。だから比較することは大事です。ただし、比較した結果、「あんたは◯◯に比べてダメね」と言うのはダメ。比較はいいが、けなすのはNG。
本当の頭の良さがテストの点数に現れるとは限らないです。計算が多いテストなら、計算ができれば点数はよくなります。(小学生の算数。特に低学年)思考力を問う問題が多ければ、思考力が高ければテストの点数がよくなる。問題の出題の仕方で点数は異なる。たかがテストの点数。本当の実力が表れるとは限らないです。定量と定性、両面見ましょう。
定量:数値ではかれるもの。
定性:数値ではかれないもの。
テストの点数が定量だとすると、定性は取り組み姿勢。テスト前に3時間×10日やったか。スマホをおかずながら勉強していないか。バツのときになぜそ
テストの点数そのものではなく、プロセスを見たい。テストの点数はプロセスをうかがいしるための道具。プロセスが目的、テストの点数は手段。目的と手段をとりちがえないことが大事だと思います。テストの点数がたまたま良くても、プロセスが悪ければ長続きしない。たまたまいい点がでてしまっただけ。テストの点数が悪ければ点数そのものがマズイのではなく、おそらくプロセスが悪い。そこがまずい。
ウチの子どもは何ができてない?どうすればいい?そんなことを考えたいですね。子ども本人に考えさせる?重要だけど、本当にできますか?子どもの反省は浅いことが多い。今回のテストの反省。
社会がわるかった。
→次回社会をもっとがんばる。
とか。
社会が悪かった根本的原因は何でしょう?
勉強時間の総量が少なかったのかも。トータル30時間やれば終わるところを、20時間しかやらなかった。だから、全教科を仕上げることに至らなかった。だとすると総量を増やさないと次回は、社会を優先すれば別の科目が仕上がらない。勉強量が足りないことが問題、とかですかね。
今回は極端に成績が悪かった。→ムキー!感情のままに子供を叱るではなく(気持ちはわかります)、なぜ成績が悪かったのかを考えるのが重要です。問題は解決できますし、問題を解決した経験が自分を成長させるのでいいチャンスです!勉強と一緒です。✕がついたらそれを○に変えたら成績アップ。✕は宝物という発想と同じです。例として成績が悪かった原因が勉強しなかったからだとしましょう。そうしたら数値化して考えましょう。いつもはテスト10日前にテスト勉強を始める。平均3時間勉強する。→合計30時間の勉強をしている。でも今回は4日前に勉強を始めた。合計12時間しか勉強しなかった。たしかに勉強量が少ない。では、なぜ今回は4日前に勉強を始めたのか?→なんとなく。とかフワッとした原因が出てくると思います。でもなんとなく、だとよくわかりません。スマホいじくっていて時間がなくなっちゃう。TikTokを見ていたらあっとういう間に時間がすぎる。ゲームしていて終わる、とかそんなとこだとしましょう。じゃあ次回もスマホでそうやっていたら同じこと繰り返すよね?じゃあどうしたらいい?
というのが対策の例になると思います。親が主導して、解決策を全部だして、子供がそれを実行するだけ、とならないようにお子さんが考えるようにするといいと思います。話を聞いてあげて、ときに提案するぐらいがいいでしょう。こうやって問題を解決できる力は、勉強だけでなくあらゆることに役立ちますよね!
偏差値・点数などの数字(定量情報)は大事ですが、数字以外の情報(定性情報)も大事です。
英語の点数が低い⇒なぜだろう?⇒文法が理解できていない⇒英語の文法を中1の内容からやりなおす。
英語の点数が低い⇒なぜだろう?⇒授業中に寝ている⇒なぜ寝るのだろう?⇒夜中にスマホでゲームしている⇒夜中にスマホでゲームしない。授業をちゃんと聞く。
英語の点数が低いことは同じですが、打ち手は変わってきます。打ち手を考えるには授業の状況(=定性情報)を見ている僕や学校の先生の話を聞くといいでしょう。ご相談ください。
今回は社会が悪かった。
→解決策:社会の勉強をあまりしなかったので、次回は社会の勉強をやる(裏返すだけの浅い解決策)
これ、うまくいくと思います?
あんまりうまくいくイメージないですよね。次回もまた社会の勉強量が少なくて社会の点数が悪いか、社会をたくさん勉強して理科の点数が悪くなったりするんですよね。
 塾長 小池哲平
塾長 小池哲平社会の勉強をなぜしなかったの?

いやー、今回は歴史が多くて、歴史は私あんまり好きじゃないので後回しにしちゃったんですよね。
 塾長 小池哲平
塾長 小池哲平なんで歴史が好きじゃないの?

んー…、暗記ばっかりでつまらないじゃないですかー。
 塾長 小池哲平
塾長 小池哲平そうなんだ。歴史モノのマンガよんだり、映画みたり、TV見たりしたことある?ゲームでもいいけど。

いやー、そういうのはないですねー。
歴史が好きじゃないから後回しになっているのが原因。だから解決策①は、歴史を好きにすることですよね。また次回も好きじゃないことがでてきたら、後回しになってそこの単元の点数が下がりますよね。(もう一つは好き嫌いに左右されずに、均等に勉強できるようにするという方法もありますが、時間がとれるならまずは好きにするアプローチをして、時間がないなら(高校入試直前など)好きじゃなくても勉強する方策を取る感じですね。)だから歴史のマンガを読んだり、歴史ゲームをしたりして歴史に興味を持つっていうのが重要ですよね。

えー、でも歴史のマンガってつまらないじゃないですか
 塾長 小池哲平
塾長 小池哲平それって学習マンガでしょ?確かにあれはあんまりおもしろくないよね。だからアレとアレをまずは読むといいよ。…
と、こういう感じで原因の裏側を考えていく。問題の本質を考えていくことが重要です。社会が悪かった→次回は社会を頑張る、みたいな解決策になってないレベルで止まっているケースが非常に多いです。

成果は質×量×スピードで決まります。
質:勉強のやり方。バツ直しを中心に勉強する。授業を目で聞く。分からなければ調べる。理解する勉強をする。
量:単純に勉強した時間。普段は1日90分。テスト前は3時間×10日間=30時間。
スピード:問題をとくスピード、文字を書くスピード。同じプリントを同時に初めて10分で終わる子。20分かかる子がいる。20分かかる子は10分の子の2倍の時間勉強してようやく同じ量勉強したことになる。
意外と軽視されがちなのはスピードです。
スピード系のアドバイスはこんなところ。普段の授業から繰り返し何度もしています。塾で使うプリントはご丁寧に、そうせよ、といちいち書いています。普段から意識してやるといいですよ。
質も高めて、量も増やして、スピードもあげる。そうできるのは理想ですが、できそうに感じなくないですか?だったらどこに問題があるか、どこなら高められそうか話してみるといいですよ。
量を増やすのはヤダ。だって遊びたいし。→ならば、質とスピードを高めよう。
質、スピードを高めるのは難しい。→じゃあ、量を増やそう。今は1日1時間の勉強をしている。ならば1時間半に増やそう。どうしたら増やせるかな?週1マストで塾の自習室に行って2時間勉強する。それなら週7時間→週9時間に量が増える。
具体化していくことが重要です。
テストの点数を平均化したがるケースがよくあります。数学100点、英語80点、理科80点、社会80点、国語60点。国語をどうにかせねば…そう思うのは自然だと思います。まあでも高校入試の仕組み上、合計点勝負なので全教科80点でも400点、数学ができて国語ができなくても400点。同じ400点ですよね。確かに60点のものを80点に伸ばすことはできても、100点を120点にすることはできないので、その考えもわからなくはないです。
テスト結果で状況をつかんだら、その後のアクションが大事。赤で答えを写して終わりが多い。わからないことを放置する子が多い。
これだと絶対にのびないです。✕をなおすのが当たり前。なおさないと気持ちわるい、という感覚を身につけたい。本来、ここは小学生のうちに身に着けておくべきこと。
✕なおしはご家庭の仕事であるという意識をもっていただきたいです。なぜなら✕の問題はお子さんによって違うから。
子どもが学校でわからなかったことや、疑問に思ったことを親に質問しないとしたら、結構まずいですよ。流す癖がついています。これおすすめです↓
お子さんの解答用紙の書き込みを見て、なぜ間違えているのかを考えてみてください。書き込み内容にヒントがあります。
なぜ計算ミスがおこるのか?計算の書き方が荒くない?
よくある例1:筆算の場合は、桁の横ずれ。十の位、一の位がゆがんでななめっている。
よくある例2:途中式をほぼ書いていない→途中式を書かないから間違える。途中式を書く。
 塾長 小池哲平
塾長 小池哲平単なる計算ミス、凡ミスで済ませないで、なぜそれが起こったのか?原因を考えて対処しましょう!同じミスを繰り返さないために。お子さんは分析しないです。具体化しないです。凡ミス。計算ミス。そんな言葉多いお子さんは危険。
コレは将来、危険なパターンです。文章を理解して考えるというプロセスを飛ばして、自分の頭にストックされている解き方(解法パターン)を頭の中で探し出し、当てはめているだけだからです。
学年が上がり、応用問題の比率が高まるとどんどん点数が下がる傾向があります。先細る子は、口癖として「解き方」「やり方」「公式」を教えてとよく言います。自分の頭で考えることを楽しめず、解放パターンの暗記で対処しているのです。
✕の分析にはもっと根本的なものもある。計算がダメ、応用がダメというのは教科の中でも問題。もっと根本的には授業の受け方が悪いというケースもある。先生の話を半分ぐらいしか聞いていない。前でみんなで演習しているときにはボーっとしている。そういう子も多い。(塾の生徒では2~3割ぐらいいます)
ではなぜボーっとしているのか?問題を深掘りしたい。
聞く力が弱いケースもある。学校の勉強は聞く力に左右される部分が多い。当塾の授業はスライドを駆使して眼で見てわかる授業が多いが、それでも「今から7分で○○のプリントを終わらせて」などの指示は口頭だ。それをほぼ100%聞けていなくて、同じ質問を何度もしてくる子がいる。
おそらく聞く力が育っていない。聞く力が問題だとして、それが解消すればあらゆることが良い方向に向く。
「なんでこんなのもできないの!」ではなく、「できないことがわかってよかったね!これで一つ成長したじゃん!」というスタンスが重要。✕→◯になおすことで成長する。
重要なのはプロセス。努力によって結果はいくらでも変えられるという視点をもつ。結果をほめると、結果が重要であるという視点がつよくなりすぎる。生まれつきの能力で決まっているという思考→✕。結果は努力によって変えられる。やるかやらないかという思考→◯
詳しくはこちら↓
同じ話なんですけど、成長マインドセットが大事ですよ-という話。メンタリストDaiGoの話が難しく感じる方は、てぃ先生の動画のほうがすっと理解できると思います。
| 成長マインドセット | 固定マインドセット |
|---|---|
| 結果は努力でいくらでも変えられる →テストの結果がよかったときに、過程を褒めることではぐくまれる。 | 結果は才能・生まれで決まっている →テストの結果自体を褒める、才能・能力を褒めることでこうなる。 |
 塾長 小池哲平
塾長 小池哲平褒めればいいってわけじゃなくて、褒め方があるんですね。
確かに、いつも能力を褒められていた子は、たまたま結果が悪いとテストの点数をかくしたり、ごまかしたりしていることが多いような…。
当塾の説明を聞きたい、勉強の相談をしたい、体験授業を受けたいという方はこちらをどうぞ。所要時間は60分程度。体験だけ、説明だけ、相談だけも大丈夫です。しつこい勧誘もしません。安心していらしてください。
\お気軽にどうぞ/